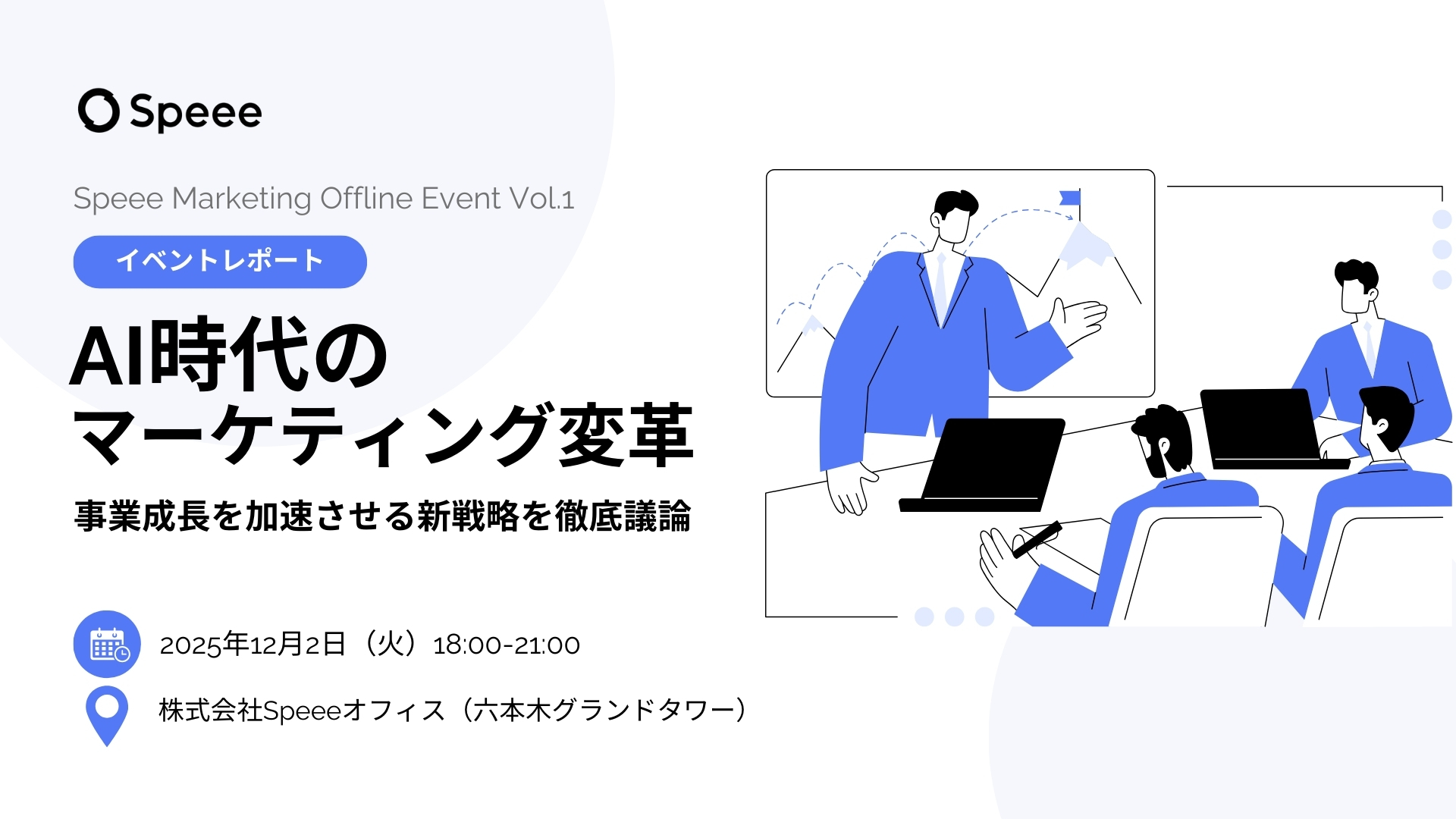AIモード とは、Google検索で利用できるAI検索機能であり、ユーザーが質問を入力することでAIによる総合的な回答を得られるモードです。これは、より高度な推論を活用してAI Overviews(AIによる概要)を拡張し、従来のSEOだけでなくAEO(回答エンジン最適化)が不可欠となる時代への移行を示唆しています。
本記事は、AIモードについて、その基本機能から、マーケティング担当者が取るべき次なる戦略までを、SpeeeのAIリサーチ&イノベーションセンター(AIRI)の知見を交えて徹底的に解説します。
AIモードとは?その基本機能と全体像を解説
AIモードとは、Google検索で利用できるAI検索機能の1つであり、ユーザーはAIモードで質問を入力することでAIによる総合的な回答を得ることが可能です。
これは、Googleが従来の検索体験をより対話的で、次のアクションに繋がりやすくするために開発している機能の一つであり、マーケターにとって、この検索行動の変化に対応するAEO(回答エンジン最適化)戦略の必要性を高めています。
AIモードとは何か?従来の検索との違い
AIモードとは、ユーザーが能動的に有効にすることで、検索結果全体をAIが整理・再構築し、より深い洞察や関連情報を提供する機能です。
検索結果の最上部に自動で生成されるAI Overviews(AIによる概要)を、ユーザーの能動的な対話によって拡張し、より詳細な情報整理や次のアクションへの誘導を強化した機能と言えます。
従来の検索結果が、ユーザーにリンクを提供し、ユーザー自身が適切な情報を見つけ出すことを求めていたのに対し、AIモードは、AIが情報を整理し、ユーザーの次の行動を促すためのガイド役として機能します。
生成AIの能力を活用し、ユーザーの複雑な質問や探求意図に対して、検索結果をテーマ別やステップ別に分類・再構築し、情報のナビゲーションを最適化するAIモードは、ユーザーの検索行動において情報発見の効率化というインパクトを持ちます。
AIモードの主要機能
AIモードの主要な機能は、検索結果の整理と、ユーザーの行動を促すための拡張機能にあります。現在確認されている主な機能は以下の通りです。
- 検索結果の整理・拡張 : AIが検索結果を分析し、関連性の高いウェブサイトの情報や画像、動画などをテーマ別やステップ別にまとめて表示します。
- ユーザーとの会話 : AIモードで表示された情報に基づき、「さらに深く掘り下げる」ためのフォローアップの質問を提案したり、ユーザーが質問を続けるための対話型インターフェースを提供します。
- 次のステップの提案 : 関連性の高い情報や行動(例:比較、購入、計画の立案)に関する追加の提案がなされ、ユーザーの行動を次のフェーズへと誘導します。
これらの機能を通じて、AIモードは検索結果をよりパーソナライズされた、行動志向の強いインターフェースへと変貌させます。

AIモードの使い方
AIモードは、テキスト、音声、画像など、マルチモーダルな方法で質問できる点が特徴です。
AIモードを利用する主な手順は以下の通りです。
AIモードへのアクセス
- google.com/ai にアクセスするか、 www.google.com で検索後に検索バーの[AIモード]タブをタップします。Googleアプリでは、ホーム画面のAIモードアイコンからもアクセス可能です。
質問の入力方法
- テキストで質問する: 画面下部にある [質問する] バーに質問を入力します。フォローアップの質問もここに入力します。
- 音声で質問する: [質問する] バーのマイクアイコンをタップし、音声で質問します。連続してマイクアイコンをタップすることで、フォローアップの質問も可能です。
- 画像を使用して質問する(Googleアプリのみ): 検索バーでレンズアイコンをタップし、画像をアップロードするか、写真を撮影します。画像に基づいた質問を追加で入力します。
回答の取得と深掘り
AIモードは、クエリファンアウトという技術を使用し、質問をサブトピックに分解して複数のデータソースを同時に検索し、統合された回答を分かりやすく提供します。
AIによる回答の品質や有用性に十分な信頼性がない場合は、回答の代わりに一連のウェブリンクが表示されることがあります。
検索履歴の再開
AIモードの 検索履歴アイコン を使うと、前回中断したところから検索を再開できます。
この対話によって、ユーザーは複数のウェブサイトを巡回することなく、AIが複数の情報を統合して生成した答えを、その場で得ることができます。マーケターはこの「対話の発生」を前提とした情報設計が不可欠です。
(参考:https://support.google.com/websearch/answer/16011537?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid)
2025年10月時点:日本での提供状況
AIモードは、2025年9月9日より順次、日本語での提供が開始されています。 日本語のほか、インドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語(ブラジル)でも提供が始まっています。
利用環境は、PCとモバイルのブラウザ、AndroidおよびiOSのGoogleアプリで、Google検索の結果ページに表示される[AIモード]タブより利用可能です。
この導入により、AI検索体験が日本国内の検索行動において、既に「普及期」に入ったといっても過言ではありません。現在のGoogle検索では、Know系クエリを中心にAI Overviewsが出現しており、その多くでAIモードへの切り替えが可能となっています。この流れは今後さらに加速し、AIを活用した検索体験が標準となる可能性が高いと言えます。
(参考:https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/ai-mode-search/)
AIモードの仕組み:コンテンツはどのように引用・参照されるのか?
AIモードは、AI Overviewsのように回答を生成するのではなく、検索結果として表示されたコンテンツを参照し、整理してユーザーに提示します。そのため、AIモードで情報源として認識されるためには、従来のSEO順位が高いことに加え、AIが情報を整理しやすいコンテンツ構造(AEO)の整備が重要となります。
AIモードが情報を「整理」するプロセスにおいて、AIはウェブ上の情報を収集・分析します。このとき、従来のSEO対策、すなわち高品質なコンテンツの作成や基本的なガイドラインの遵守が引き続き重要となります。AIは、LLMO(大規模言語モデル最適化)の技術を活用して、ウェブ上の大量の情報、特に検索結果の上位に表示されている信頼性の高いウェブサイトから情報を収集します。
AIに情報源として採用されるためには、単にSEO順位1位を獲得するだけでなく、AIが迅速に情報を分類・参照できるように、コンテンツ設計が極めて重要になります。
AIモードはマーケティングにどのような影響と課題をもたらすのか?
AIモードの本格導入は、ユーザーの検索行動の「ゼロクリック化」を加速させ、オーガニック流入の減少という課題をもたらす一方で、AIによるナーチャリング機能を通じて、コンバージョン(CV)に繋がる質の高い見込み顧客を獲得する新たなチャンスを生み出します。
マーケターは、この変化を単なる脅威として捉えるのではなく、事業成長の機会として活用することが可能です。
従来のSEO対策とAIモード対策(AEO)の違い
AIモード(およびAI検索全体)の登場により、従来のSEO(検索エンジン最適化)に加え、AEO(回答エンジン最適化)という新しい対策の概念が必須となりました。AEOは、AI検索の結果(AI OverviewsやAIモードによる整理)で、自社コンテンツを情報源として引用させ、推奨されることを目的としています。
従来のSEO対策(ランキング向上)は、AIが情報を収集する足がかりとして引き続き重要です。しかし、AI時代に勝ち抜くためには、その上位表示されたコンテンツがAIに回答や整理情報として採用されるためのAEO施策が不可欠となります。
【Speee独自知見】AI時代に事業成長を加速させるAEO戦略とは?
短期的な流行に惑わされず、ファクトに基づいた長期的なAEO戦略を構築することが、AI時代における事業成長の鍵です。Speeeでは、AIがユーザーへコンテンツを推奨するプロセスを分析し、効率的な施策実行を可能にする独自戦略を提唱します。
AIが推奨する仕組み「AIレコメンデーションファネル」
AIがコンテンツを「発見」してからユーザーの「コンバージョン」に至るまでの複雑な経路を、SpeeeではAIレコメンデーションファネルとして体系化し、4つのフェーズに分けて戦略を策定します。
- 第1段階:AIに見つけてもらう
AIが参照すべき情報源の候補リストに自社サイトを確実に含める。 - 第2段階:AIに理解してもらう
AIが自社サイトの内容を正確に解釈し、要約や引用に利用できるように情報の構造と記述を最適化する。 - 第3段階:AIに推奨してもらう
AIが多数の情報源の中から自社サイトを「最も信頼性が高い、引用すべき情報」として評価し、優先的に選択する。 - 第4段階:AI推奨をCVに繋げる
AIによる推奨内容とランディングページの内容に整合性を持たせ、CVRを最大化する導線を設計する。

各段階で取り組むべき具体的な施策
【第1段階:AIに見つけてもらう】検索結果の上位表示とLLMに優先的に読まれる工夫
目的:
- 検索結果の上位表示を達成し、AIが数ある候補の中から自社サイトを 優先的に読み込む状態 を作る。
主な施策:
- XMLサイトマップの最適化: AIクローラーに情報の新しさと網羅性を迅速に伝達する。
- コンテンツのニーズメット追求: ユーザーの検索意図に過不足なく答え、AIに「最も適切な情報源」と評価させる。
- タイトル・ディスクリプションの最適化: タイトルやメタ情報で「公式」「最新情報」を明記し、権威性をアピールする。
- 公式サイトの同時更新: プレスリリースなどに合わせ、公式サイトも同時に更新し、情報の鮮度と詳細な情報源があることを示す。
【第2段階:AIに理解してもらう】AIが効率よく解釈できる構造化された記述
目的:
- AIが文章全体ではなく、価値のある部分だけを効率よく解釈できるよう、コンテンツの構造化を支援する。
主な施策:
- 構造化データの適切な活用: FAQPageスキーマやHowToスキーマなどでAIの理解を支援する。
- 引用されやすい記述方法の工夫:各セクションの冒頭で結論ファーストの簡潔な文章を配置する。箇条書きや表形式でエッセンスをまとめ、AIによるピンポイントな情報抽出を助ける。
【第3段階:AIに推奨してもらう】E-E-A-Tの向上と第三者からの評価獲得
目的:
- AIに「最も信頼でき、推奨に足る情報源である」と総合的に判断させるために、信頼性と権威性を強化する。
主な施策:
- E-E-A-Tの強化: 専門家の起用、監修体制の明記、引用元の情報や客観的な数値データの明確な提示により、AIへの信頼性を強化する。
- 第三者サイト評価向上: 外部の権威あるサイトからの言及や引用を増やし、比較・レビューサイトで優位な評価を獲得することで、Web上での権威性を高める。
【第4段階:AI推奨をCVに繋げる】AIが推奨する内容とLPの整合性
目的:
- AIの推奨によってサイトへ流入したユーザーの期待値とのギャップをなくし、離脱を防いでCVRを最大化する。
主な施策:
- AI推奨内容の把握と分析: AIが自社製品・サービスをどのような文脈、メリットで推奨しているかを分析する。
- ファーストビュー・LP最適化: AIが推奨した具体的な内容と、CV先のランディングページ(LP)の訴求内容を完全に一致させ、ユーザーの期待値とのズレを解消する。
- CTAボタン配置最適化: ユーザーの認知負荷を最小限に抑えるよう、CVに直結するCTAボタンを最適な箇所に配置する。
成果を測るSpeee独自の指標:「AIインパクトスコア」と「AI Visibility Score™」
AI時代のマーケティング投資の合理性を担保するためには、従来のトラフィックやCVRといった指標に加え、AIモードを含むAIプロダクト・機能の影響を直接測定する新しいKPIが必要です。Speeeでは、AEO戦略の成果を測るために、以下の独自指標(KPI)を導入しています。
AI Visibility Score™
AI Visibility Score™は、対話型AIエージェントの構造に則して、推奨率に関わる因子ごとの想定評価を可視化したSpeee独自指標です。
対話型AIエージェントは、LLMを使い、外部情報を検索・参照してユーザーの質問に答えるシステムです。Speeeでは、処理フローごとに詳細に計測することで、課題発見と効果検証の精度を向上させています。


AI Visibility Score™ (AVS)とは? AI検索のブラックボックスを解明する、SpeeeのAEO独自メソッドの中核指標
AI Visibility Score™ (AVS)とは、AI検索における企業の「見つけられやすさ」や「推奨されやすさ」を定量化するSpeee独自の指標です。ブラックボックス化しているAIの回答生成プロセスを可視化し、AEO対策のボトルネック特定を可能にします。
AIインパクトスコア
AIインパクトスコアは、AI経由のトラフィックが、直接・間接問わず、最終的な事業成果にどの程度貢献しているかを測るSpeee独自指標です。
AI経由でのダイレクトな成果だけでなく、AIによって意欲が高まったユーザーが指名検索をしたり、ほかチャネル経由でCVするといった間接的な影響まで包括的にモニタリングします。
AIによる回答・推奨が事業の利益に直結しているかを評価し、AEO投資のROI(費用対効果)を正確に把握するために不可欠です。

まとめ:AIモードの動向を踏まえた、マーケティング担当者の次なる行動指針
Google検索のAIモードの日本正式導入は、マーケティング戦略全体を見直す契機となっています。AIによる回答が主流となる時代において、「ゼロクリック化」を避け、事業グロースを継続するためには、従来のSEOの延長線上にAEO(AI検索最適化)を組み込むことが不可欠です。
一方で、マーケティング担当者が今取るべき行動指針は、「過度に焦らず、ファクトに基づき、動向を注視しながらAEOの準備を着実に進める」というスタンスです。
データに基づいた仮説検証
AI検索の判断メカニズムは複雑であり、似たような施策の失敗ケースでも、ボトルネックとなっているメカニズムが異なれば、対策も変わってきます。重要なのは、「効く」とされる施策をただ実行するのではなく、AI Visibility Score™やAIインパクトスコアといったKPIを用いて、「今どこがボトルネックになっているのか」をデータに基づいて特定し、仮説を検証していくことです。
検索の本質を捉える
AIO/AEO対策は、単なるAI向けのテクニックではなく、ユーザーが求める情報に対して、より深く、より信頼性の高い「一次情報源」となるための取り組みです。E-E-A-Tの強化や、ユーザーの検索意図をとらえたコンテンツ設計など、検索の本質を捉えた質の高い戦略が、AI時代においても成果創出の鍵となります。
PDCAを回す重要性
AI検索市場は日々進化しており、対話型AIツールをはじめとして、AIモードやAI Overviewsの仕様も常に変化しています。この流動的な環境で成果を出し続けるためには、施策を実行し、成果をKPIで評価し、それを次の戦略に活かすというPDCAサイクルを高速で回し、AI時代の最前線で事業成長を加速させることが不可欠です。
お困りごとはSpeeeにご相談ください
AI時代のマーケティング戦略は、これまでのSEOの知見に加え、AI技術への深い理解が必要です。SpeeeのAEOコンサルティングは、業界最大規模のAIリサーチ&イノベーションセンターが持つ技術的な裏付けと、長年のSEO事業で培った実行力を融合させ、お客様の事業に貢献する成果にコミットします。
ゼロクリック化による集客減少の懸念、AI時代の新たなCVルートの確立など、お困りごとがございましたら、ぜひ一度Speeeにご相談ください。
FAQ
- Q1. Google検索の「AIモード」とは何ですか?従来の検索とはどう異なりますか?
- A1. AIモードは、ユーザーの質問に対しAIによる総合的な回答を得られる、Google検索のAI機能です。従来の検索がリンクを提供したのに対し、AIモードはAIが情報を整理・再構築し、ユーザーの次の行動を促すガイド役として機能します。
- Q2. AIモードがマーケティングにもたらす影響と課題は何ですか?
- A2. AIモードの本格導入は、ユーザー検索行動の「ゼロクリック化」を加速させ、オーガニック流入減少のリスクを高めます。一方で、AIによるナーチャリング機能を通じて、コンバージョン(CV)に繋がる質の高い見込み顧客を獲得する新たなチャンスも生み出します。
- Q3. AIモードが利用される時代において、SEOとAEOはどのように役割分担されますか?
- A3. 従来のSEO(ランキング向上)は、AIが情報を収集するための足がかりとして引き続き重要です。しかし、AI時代により事業を伸ばしていく、マーケティング成果を上げるためには、その上位コンテンツがAIに引用・推奨されるためのAEO(回答エンジン最適化)施策が不可欠となります。AEOは、AIが情報を処理し推奨するプロセスに最適化することを目指します。
- Q4. AIにコンテンツを情報源として「発見」させ、「理解」させるための施策は何ですか?
- A4. 発見(見つけてもらう)のためには、XMLサイトマップの最適化や、タイトル・メタ情報で「公式」「最新情報」を明記し権威性をアピールします。理解(理解してもらう)のためには、構造化データ活用や、結論ファーストの記述、箇条書きなどで、AIが効率よく解釈できるコンテンツ構造を整備します。
- Q5. AIに「最も信頼できる情報源」として優先的に推奨してもらうための施策は何ですか?
- A5. コンテンツの信頼性(E-E-A-T)と外部評価の強化が中心です。具体的には、専門家の起用、監修体制の明記によるE-E-A-Tの強化、客観的な数値データの明確な提示により、信頼性を高めます。さらに、外部の権威あるサイトからの言及を増やし、Web上での評価を向上させます。
著者・監修者情報
監修: Speee AIリサーチ&イノベーションセンター(AIRI)
事業と連携してAIソリューション開発を進めるために 設立された機関。 研究、技術開発、そして実証実験までを一貫して実施。業界を牽引するAIスペシャリストと総勢50名以上のアナリストが所属しており、 大量の実案件ベースのデータを活用しながら、業界を牽引するAIソリューションを生み出し続ける。
CSIO(Chief Strategy&Innovation Officer) 渡邊 洋介
AI時代のマーケティング変革を専門とする実践者・研究者。Speeeでは13年間、国内最大規模のSEO事業においてアルゴリズム解析と大規模実験を通じた知見蓄積を主導し、現在はAIエージェント時代のマーケティング変革に取り組んでいる。
CAIO(Chief AI Officer) 和田 和久
Amazon Japan、AWSを経てSpeeeにjoin。現在はSpeeeマーケティングDX事業領域の開発責任者およびAI リサーチ&イノベーションセンター技術責任者として、AI研究開発、技術経営を管掌。